
ビジョンを成果につなぐ―明確な目標が人と組織を動かす
あっという間に年末が近づいてきました。新しい年の計画や、組織・チーム目標の設定など「来年はもっと成果を出そう!」と思いをめぐらす時期でもあります。今回は「その目標、本当に“明確”ですか?」をテーマに、米国ブランチャード社のマドレーヌ・ホーマン・ブランチャード(マスター認定コーチ)の語りを、プログラムディレクターのデイビッド・ウィットが紹介しています。原文はこちら
パフォーマンス向上のカギは目標設定です。しかし多くの人は「自分は目標設定が得意」だと思っているので、それを軽視してしまいがちです。
現実はこうです-------------多くの人は「やりたいこと」のイメージは持っていますが、具体的な目標や計画が曖昧なままスタートしています。
目標を設定しないことは、一度も行ったことのない場所へ、GPSに住所を入力せずに行こうとするようなものです。明確な目的地がなければ、迷うのは当然のこと。 これは組織内でも起こりがちなことです。リーダーは「メンバーは目指すべきところがわかっている」と考えがちですが、実際は違います。旅をするなら、まずゴールにピンを刺しましょう。明確な目標は、私たちがフォーカスすべきこと、優先すべきことを教えてくれます。
当たり前のことを言っているように思えるかもしれませんが、特定の場所に向けてドライブするのと、ただドライブを楽しむことは違います。もちろんドライブを楽しむのは悪いことではありませんが、それはプライベートの時間に楽しむものです。
目標設定によってメンバーと組織をつなげる
明確さと良いコミュニケーションがあれば、メンバーと組織がつながります。リーダーの役割は、個々の業務と全体の戦略や目的をつなぐ“一本の線”を示すことです。
「見ればわかるから」と曖昧な指示をするリーダーがよくいますが、 これはメンバーの力を削ぐ最悪のやり方です。ブランチャードではこれを「石当てゲーム(Rock Game)」と呼んでいます。
「石を持ってきて」と頼まれ、持っていくと「もう少し大きいの」「もう少し丸いの」と修正され続ける。部下は思います『最初から“直径5インチの黒くて丸い石”と言ってくれればずっと簡単だったのに....』と。メンバーに良い仕事をさせるには、リーダーが成功のイメージを具体的に言語化することが欠かせません。
明確な目標は、エンパワーメントの土台
明確な目標は、時間を節約するだけでなく、エンパワーメントを高めます。期待が明確であれば、人は自ら判断し、責任を持って動くことができるのです。エンパワーメントは曖昧さではなく、規律から生まれます。マネージャーと部下が、現実的で達成可能な目標を共に設定し、必要なサポートを話し合うことが、信頼と自立が育つのです。
明確な目標があると、急に新しい指示が降ってきたときでも、その優先順位を冷静に判断できます。「いまの目標リストのどこに位置づけるべきか?」と確認できるからです。
優秀な社員ほど「君なら何でもできるよ」と仕事をどんどん振られがちですが、限界を超えれば当然キャパオーバーします。すべてが最優先なら、何も優先できません。 だからこそ、明確な目標が優先順位づけに不可欠なのです。
目標があれば、フィードバックも責任もブレない
明確な目標があると、何を基準に評価し、何を改善すべきかがはっきりします。ただ現実には、多くのマネージャーは、
「関係が悪くなるのが怖い」
「どう伝えればいいかわからない」
といった理由で、フィードバックを避けてしまいがちです。
コーチとして依頼を受けるとき、私は必ず確認します。
「その人に必要なフィードバックはすでに伝えられているか?」
「期待に達していないことをきちんと伝えられていか?」
しかし、 ほとんどの場合、答えは「NO」です。 そもそも 期待が明確に示されていないし、フィードバックもされていないのです。
コーチングは、マネージャーが担うべき 明確な目標設定と実行可能なフィードバックの代わりにはなりません。人が変わるのは、「このままではまずい」と本人が気づいたとき。その気づきは、明確な目標設定から始まるのです。
明確な目標が、やる気と自信を生む
ブランチャードのSLII®モデルでは、コミットメント「意欲」とは特定の目標やタスクに対して実行するためのやる気と自信の指標です。もう一つの指標、コンピテンシー「技能」と組み合わせて、メンバーの開発レベルを診断します。
自信は小さな成功体験の積み重ねから生まれます。 目標を設定し、少しずつ前進し、できるようになると、 脳内でドーパミンが分泌され、モチベーションと集中力の維持、そして行動の強化、さらなる努力につながっていくのです。自信は、小さな成功体験から生まれます。
たとえば、目標を設定して達成すること、新しいスキルを学び少しずつ上達するといったことです。そうやってできた/できなかったハシゴをのぼりながら、挑戦して成功するたび、あるいは失敗して改善するたびに、自身が積み重なり、さらなる挑戦につながっていくのです。そして挑戦を続けるからこそ、能力も高まっていきます。
目標設定のコツ
目標設定のステップは、頭では理解できても、その難しさは過小評価されがちです。
脳は未来を具体的に想像することが苦手で、認知にも負荷がかかります。目標を設定する際には前頭前野をフル稼働させる作業なので、脳が最も冴えているタイミングで行うべきです。
また、過去に目標を設定し達成した経験があるほど「次も簡単にできる」と思いがちですが、実際にはそうではありません。練習によって改善はしますが、目標設定には常に時間とエネルギー、そして心身のリソースが必要です。将来を具体的に思い描くことは困難ですが、欠かすことはできません。ポイントは、「この目標を達成したとわかるのはいつ、どうなった時か」を文章として完結させることです。
目標設定は地味で手間がかかる作業ですが、成功の礎となるものです。目標は必ず書き出し、毎日確認するようにしましょう。目に入る場所に置き、スクリーンセーバーに設定する、または紙に印刷してデスクの前に貼り、物で隠さないようにするなど工夫してみてください。
メンバーにも同様に目標を書き出してもらい、1on1ミーティングの基盤として活用しましょう。「目標なんか忘れっこない」と思いがちですが、実際には忘れがちです。また、状況の変化や新たな情報に応じて目標を修正することも見落としがちです。仕事に追われて注意がそれることもありますし、プレッシャーで手が回らないこともありがちなことです。
目標設定ができた後は、脳のモチベーションを高めることも意識しましょう。たとえ小さな成功であっても祝福するようにして、モチベーションを強化し、自信を高めましょう。わたしたちは目標を達成しても振り返らずに次へ進んでしまいがちですが、それはもったいないことです。
最後に、目標はシンプルで明確なものにしましょう。人が目標を達成できない主な理由は2つあります。ひとつめは目標が多すぎること、ふたつめは目標達成に必要な支援を受けられていないことです。インパクトの大きい少数の目標に集中することが重要です。そして、達成したら必ず称賛します。達成しても褒められないと、感情が、喜びではなく「安堵」にとどまってしまいます。目標は人を追い詰めるものではなく、力を与えるものであるべきです。
----------------------------------------------------------
著者について

デイビッド・ウィットは、ブランチャード社のプログラムディレクターです。受賞歴のあるリサーチャーであり、同社の月例ウェビナーシリーズのホストも務めています。また、デビッドは『Fast Company』、『Human Resource Development Review』、『Chief Learning Officer』、『US Business Review』などに記事を執筆または共著しています
目標設定のスキルを身に付ける!「SLII®公開講座(対面)」はこちら
オンラインで学びたい!「SLII®公開講座(バーチャル版)」はこちら

年頭のご挨拶(代表取締役 松村卓朗)~PFCの2025年から2026年にかけてのトピック/キーワード~
新年あけましておめでとうございます。旧年中は、皆さま方には大変お世話になり、ありがとうございました。*PFCとは、ブランチャード・ジャパンの母体で、株式会社ピー

2025年の注目事例まとめと、2026年 SLII®3.0 へ進化
2025年もあっという間に終わろうとしています。今年も多くの企業さまで、組織づくりやリーダーシップの取り組みが進み、さまざまな成果が生まれました。本号では、20
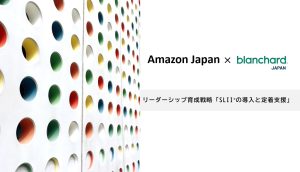
【事例紹介】Amazonのリーダーシップ育成戦略「SLII®の導入と定着支援」
Amazon Japan合同会社 オペレーション人事部 HRビジネスパートナーの伊藤 裕一 様に、「AmazonにおけるSLII®の展開」と題してお話を伺いまし
